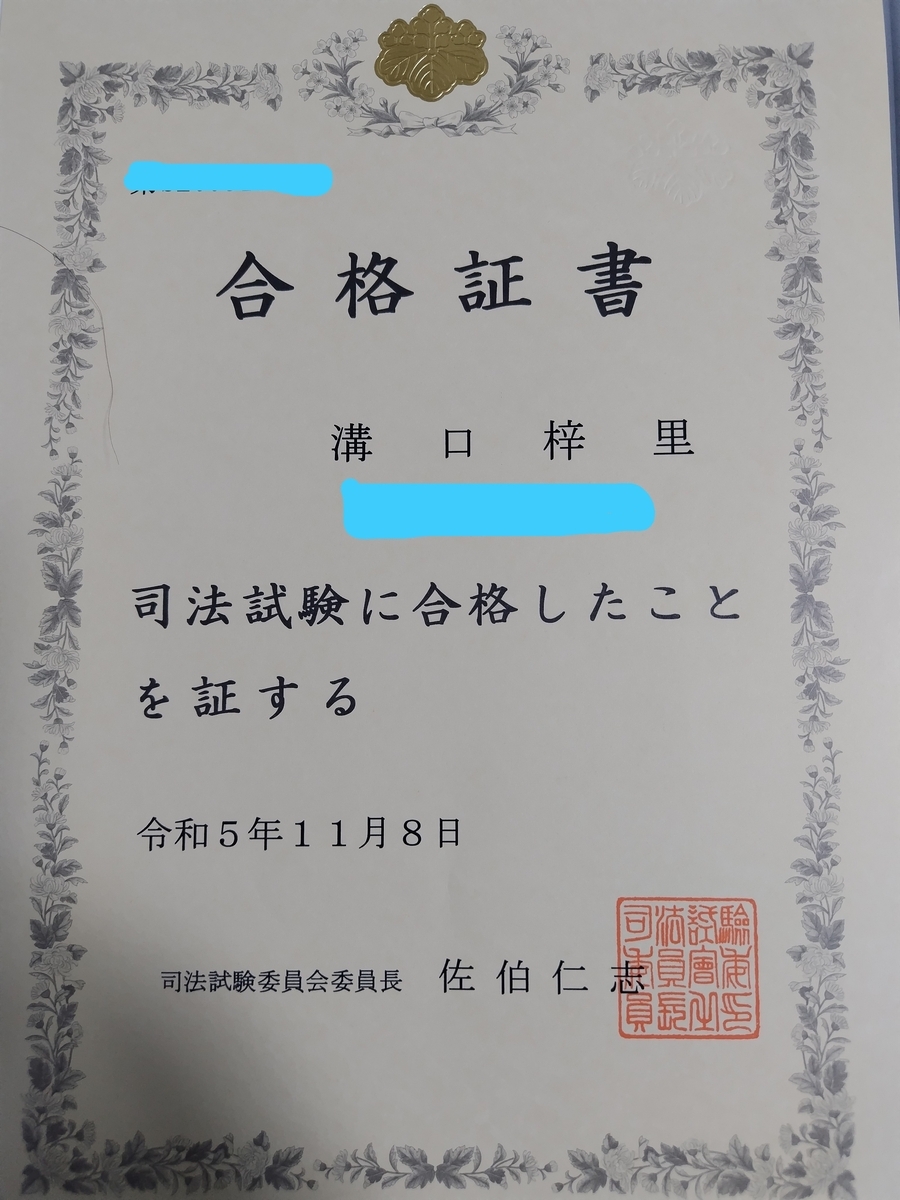
第1 総論
本日は令和6年の司法試験の合格発表日である。
私は司法試験合格にもその後の諸手続きにもそれなりに多くの思い出があるが、わざわざ世間に語るべき話は少ない。性格上あまり先輩面もしたくないし、過去の成功体験にこだわって未来への精進を怠りたくもない。
それでも例外的に合格者諸氏諸氏のお役に立てそうな体験談が一つだけあるので、本稿では大急ぎでそれのみを伝えておく。
第2 不動産屋との思い出
修習地が決まったあと、現地の不動産屋と連絡をとり「この条件で探して」と依頼をした。
不動産屋からは年収を証明できる書類を出せと言われたので、当初の私は馬鹿正直に司法修習生の採用通知のコピーだけを送った。これで修習生としての給付金や住居手当を証明したわけである。
しかしその数日後に「ちなみにそのまた翌年以降の年収を推定させるものとして、内定通知書もありますよ」と電話で語ったら、「大急ぎでそのデータも送って!」と言われた。
後知恵でよくよく考えたら当たり前の話である。まず「司法修習生」なんてものの世間での知名度は低く、その名称を知っている人でも「年収とは別に、ほぼ無条件・無利息で毎月10万円借りられる地位である」ということまで知っていることは稀である。かつ現代の大家は借地借家法のせいでそう簡単に借家人を追い出せないのである。だから「一年後に無職になるかもしれない年収約200万円の得体の知れない人物」だと思われてしまうのは大損である。
もちろん「司法修習生とは何であるか」や「その就職率と翌年以降の平均年収」を知っている凄腕の大家や賃貸保証会社も多いのであろうが、選択肢をより広げるためには、凄腕ではない人にまで自分を信用してもらうための情報を自発的にどんどん提供すべきであったのだ。
今の住所に住めることになったことが内定通知書の威力があってこそだったか否かまではブラックボックスであるが、不動産屋との雑談の中で偶然にも内定通知書の話を出したのは確率論的に考えて「会心の一撃」だったと思っている。
内定先には感謝したいことが数多くあるが、このエピソードもまたその一つである。
第3 教訓
この一件から、以後の司法試験合格者諸氏のお役に立てそうな二つの教訓を得た。
「裁判官・検察官・即独・非法曹が第一志望だったとしても、修習地が決まるまでに就活をして、内定通知書をもらっておくに越したことはない。少なくともお部屋探しをスムーズにする効果がある」
「自分ではその地方の物件に約一年間しか住まないつもりであっても、折角学んだ借地借家法の知識を活用して貸す側の立場も考えるべきである。そして内定通知書を既に持っているのならば、その話題を自分から出すべきである」








